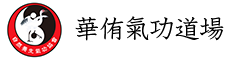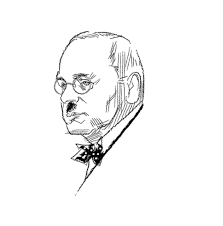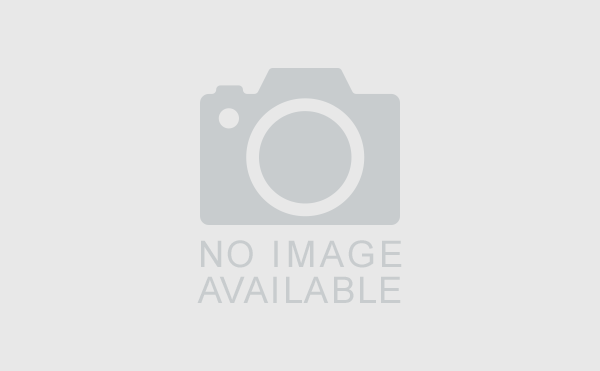何故人は願望を抱くのか
有ると無い
こんな風に思ったことはないですか
「もうこれでいいんだ、すべてのものに恵まれている、だから何も欲しい物は無い」
「とりあえず生活できているし文句を言ったらきりがない」
「上を見たらきりがない私よりもっと困っている人が世の中には多いはずだ」
「分相応な暮らしが一番」
「多くを望むことはバチが当たる」
「〇〇さんよりはマシ」
何かの不足を感じた時こんな風に自分を納得させたことはありませんか
また他人がこのような話をしているのを聞いたことはないでしょうか
それから
「もっとお金が欲しい」
「もっと思い通りの生き方がしたい」
「もっといい暮らしがしたい」
「もっといい仕事に就きたい」
「何故私は幸せになれないのか」
「何故〇〇さんは恵まれているのか」
「何故私はいつも苦労をするのか」
と不足と世の中の理不尽さを嘆いたことや聞かされたことはありませんか
同じ人間の中で「有ると無い」が常に交錯しているのを見て取ることができます
それは無意識のうちに
不足を感じても今すぐどうする事も出来ないから、現状から逃げるために「もう足りている」と思う事で自分の中の「何か」と「何か」を相殺しようとしているのかも…
その「何か」とはいったい何なのだろう…
足るを知る
聖人君子的発想は子育て中の母親にとって優れたアイテムでもある
「身の丈で生きよ」という思いは親が子を思っての発想だと思う
人は自立ができるようになる年頃まで親や学校の先生、周りの大人達の考え方で育てられます
それはどこの国に生まれたなどに関係なくどんな人も幼少期はごく少数の人達の考え方に偏ります また親は子のためを思って子育てをしながらその頃の風潮を自然に生活や育児に取り込んでいきます
※「足るを知る」とは老子の言葉で、「足るを知るものは富む」と老子は説いています
分相応に満足して生きる事、不平不満を口にするものは幸せになれない…と
何故人はもっと上を目指したがるのか
それは
人は成長したいと願う生き物だからなのです
森羅万象の生物すべてが“成長し続ける”という宿命だから立ち止まる事ができないのです
もし成長が止まってしまえばそれは“死”に至るでしょう
私達がもっと上へもっと上へと目指すのは自然の摂理なのです
いくら自分に“もうこのままでよい”と言い聞かせても時間が経つとまた成長したがるのです
日本でも中国でも戦国時代の最中なら生きていくだけで精一杯だろうから「足るを知る」は最も清く正しかっただろうと思います
今2024年の平和な日本において「なりたいものになる」「ほしい物を所有する」ことができるのは最高のチャンスだと思うのです
次回につづく